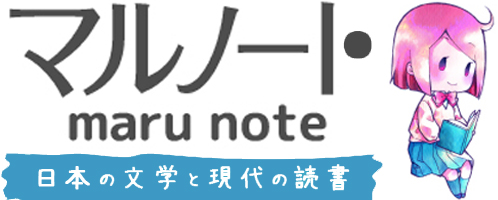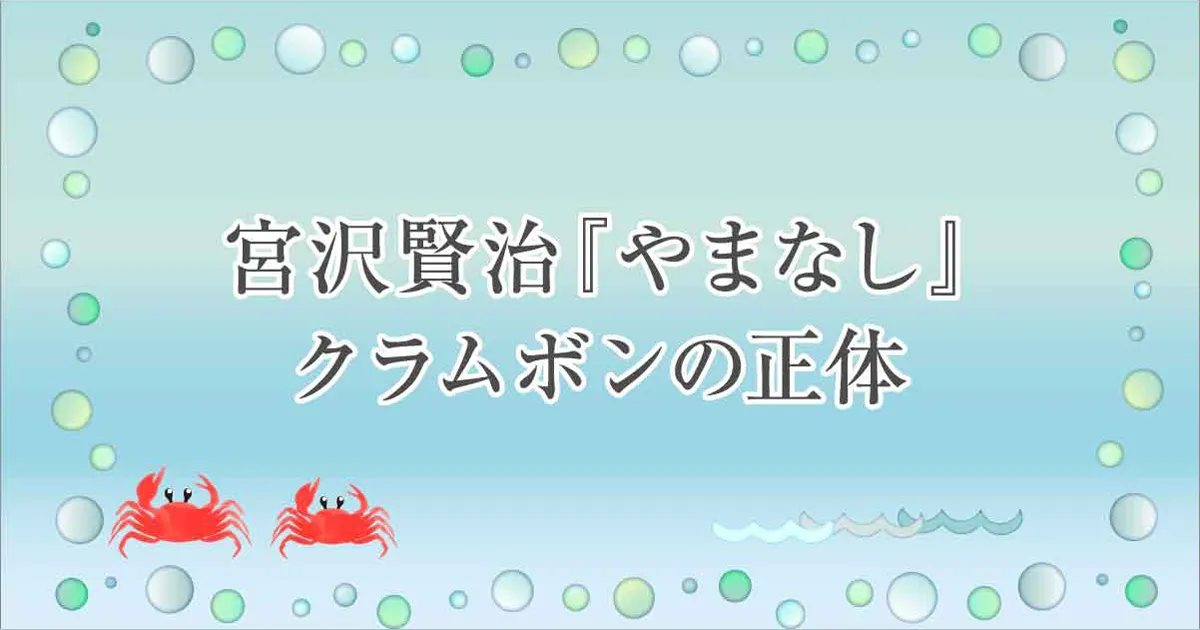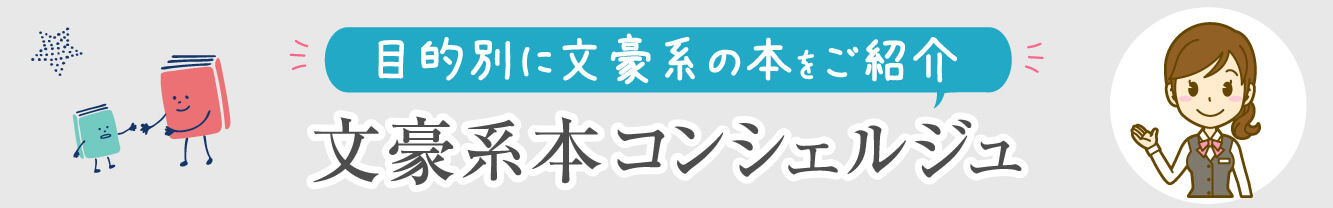宮沢賢治の『やまなし』は、小学校6年の光村図書の国語教科書にずっと採用されている作品です。

クラムボンって結局なんだかわからない…💧
そう思ってネット検索したあなたへ。
この記事では、大学で文学を専門に学んできた私が、その正体について「クラムボン=水に映った太陽」という説とその理由を4つの視点から考察します。
教科書では教えてくれない、でも納得できる答え。読み終えたあと、きっと
「そうかも…!😊」
と思ってもらえるように説明していきます。
クラムボンの正体は「水に映った太陽」
結論から先に。「今、私の考えるクラムボンの正体」についてお話します。
私の思うクラムボンとは、カニの眼から見て天井の水面にある、「水に映った太陽」。
画像でいうとこちら。





私は小学生の時は泡派、その後プランクトン派だったんですが、今は「水に映った太陽派」で落ち着きました。
クラムボンが「水に映った太陽」である理由
これから、「クラムボンとは水に映った太陽」と思う理由を4つお話します。
理由1:他が日本語なのに「クラムボン」だけ「蟹語」のまま
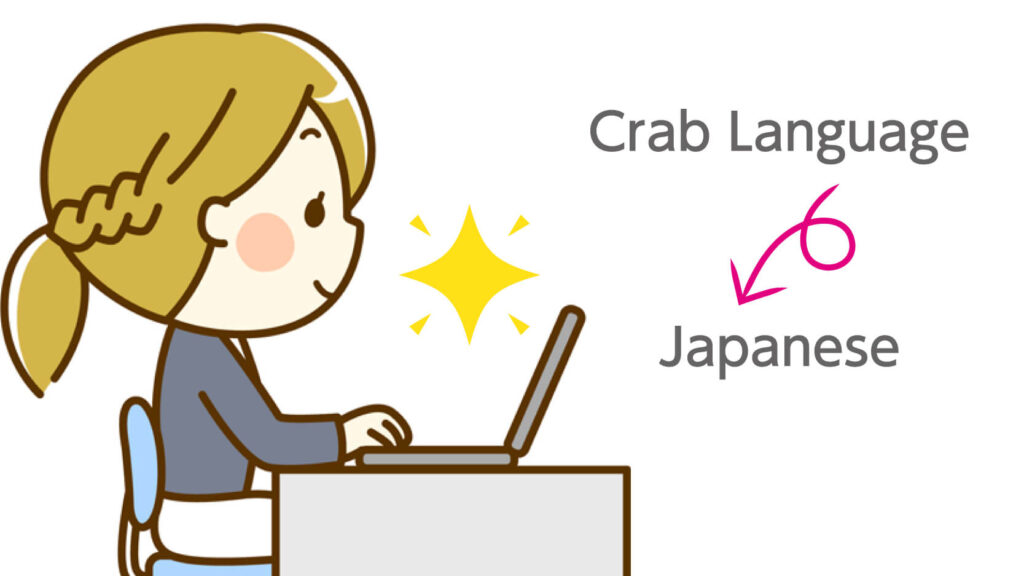
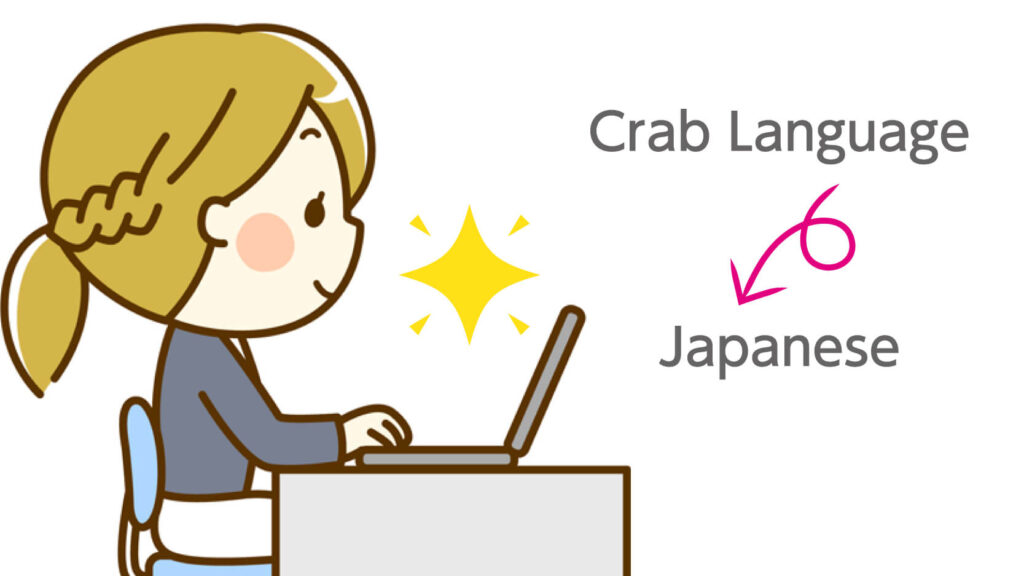
クラムボンの正体はいままでいろいろと考察されています。
正体の考察がまとめられたこのページを見ると、クラムボンは、アメンボ・プランクトン・泡・光・母蟹などいろいろな説があるそう。
その中に「クラムボン=蟹語で言われている何か」という説があります。



クラムボン = 蟹語で表現されている何か
クラムボンは蟹語です。
そして、蟹語だからわからない、という説と、蟹語だけど何なんだろう、という説に分かれます。
けれど今回は、さらに、



…なんでここだけ蟹語が残ってるの???
と考えてみます。
『やまなし』はカニの兄弟の生活を、「二枚の青い幻燈」として映し出した作品。
今で言うと映画のようなもの。
「クラムボン」が蟹語なら、蟹語は存在していて、本当はカニの兄弟の言葉はすべて蟹語で話しているはず。
そしてその言葉は私たち人間にはわからないはずです。
けれど、幻燈なのですべての言葉が人間にわかるように翻訳されています。



映画だったら、海外の映画が吹き替えになっている感じ?
だけど「クラムボン」はそのまま。
なのでクラムボンは
人間の言葉にうまく翻訳できないから、「クラムボン」のまま
なんだと思います。
この時点で、蟹の兄弟の住む世界にあり、人間も知っている水中や水面に関わる言葉「アメンボ・プランクトン・泡・光」などは普通に翻訳できるので候補から外します。
理由2:カニの兄弟が「太陽」を知らないから「クラムボン」



「水に映った太陽」だって翻訳できるんじゃない?
「水に映ったおひさまが、かぷかぷ笑ってるよ」とか…
カニの兄弟は、地上のものであるカワセミもやまなしも知りませんでした。
カワセミが魚をとった後、どこに行ったかもわかりません。水面のさらに上のことは、知らないのです。
たとえばここでカニが「水に映ったおひさまが、笑ってるよ」と言ったとします。
たとえば…
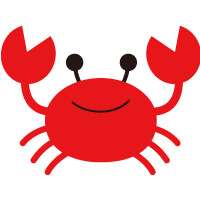
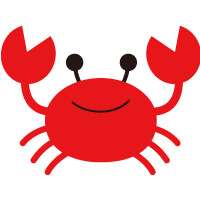
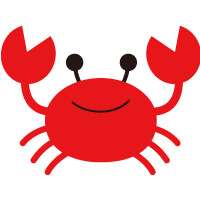
水に映ったおひさまが、笑ってるよ
↑ これはカニの兄弟には言える???
こう言うことのできるカニは、太陽の本体を知っているカニです。
水面よりさらに上に太陽にあって、水面の上の光の環はそれを映したものだ、とわかってることになります。
それがわかってやっと「水に映ったおひさま」ということができます。


カニの兄弟は地上のことを知らないので、水に映ったおひさまを太陽の映り込みとは思いません。
その映り込みを、そのもの=本体だと思ってます。
それが「クラムボン」です。
カニの兄弟に「水に映ったおひさま」と言わせてしまうと兄弟の理解している内容がおかしくなってしまいます。
日本語では「水に映った太陽」を、「太陽」を使わずに表す言葉はありません。
だからここでは蟹語そのままの「クラムボン」を使用しているんだと思います。
理由3:「クラムボン=泡や虫」ではない
冒頭からの流れを見ると、2匹は同時に同じように反応しています。
クラムボンの笑い、死、笑い、という反応は2匹の間でズレがありません。
もしクラムボンが「泡・虫」などの複数だったら、このような反応にはなりません。
あっちではこうだよ、でもこっちだはこうだよ、とズレがでてくるはずです。
ここはクラムボンが1つのまとまりであるという理由です。
理由4:カニの生活に不可欠!兄弟はクラムボンが「大好き」
カニの兄弟はクラムボンのことをしきりに話題にしています。
「クラムボンがかぷかぷ笑った」はカニにとっての天井で、水面の太陽が光ってゆらゆら揺れている様子だと思います。
魚がやってきて水面が乱され形が壊れてしまうと、「死んでしまった」と感じます。
その魚がいなくなって、クラムボンの形が元に戻ると、また「笑った」と話題にします。
カニの兄弟にとってクラムボンが殺され、生き返るのは繰り返されてきたこと。
「殺された」といいつつ、カニの兄弟はこの時点では「死」についてあまりわかっていません。
その後の、実際に魚がカワセミに捕られいなくなった後の様子と比べると怯えの様子が明らかに違います。
カワセミが来るということは、この場所は浅い池か川。そんなに深くありません。
太陽の環は天気がいい日はいつも身近にあったはずです。


水面に太陽の環がある日はぽかぽかして気持ちいい。
水面に太陽の環がない日は冷たい・荒れてる。
太陽の環はいつでも天井にあって、いい陽気といい気持ちをもたらしてくれます。
そんな太陽の環をカニの兄弟はきっと特別に思っています。だから「クラムボン」と名前を付けたのだと思います。
カニの兄弟がここまでクラムボンを話題にするのは、それがカニにとっても重要だからです。
あまり重要でないもの・自分の生活に直接影響しないものだったら、カニは話題にすらしないし、その変化にしんみりしたり、生き生きとしていることに嬉しくなったりしないのではないでしょうか。



と、いうわけで私はクラムボンは「蟹語で『水面に映った太陽』のこと」と考えます。
皆さんはどう考えますか?
宮沢賢治の頭の中を再現してみる──クラムボン誕生の瞬間とは?
今まで物語の内容から、「クラムボンの正体」を探ってきました。
次に、「クラムボン」という言葉を生んだ時の、宮沢賢治の頭の中を想像してみます。
その際には、逆に次のようなことが行われていたと私は思ってます。
まず、賢治が蟹の住むような池の写真を見ます。
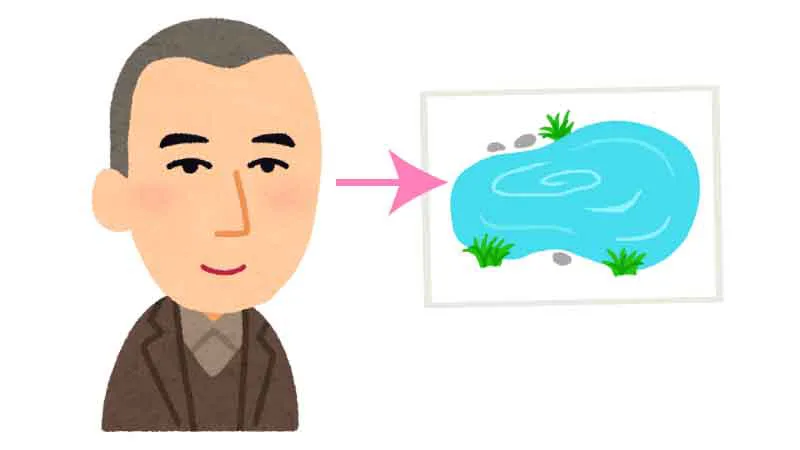
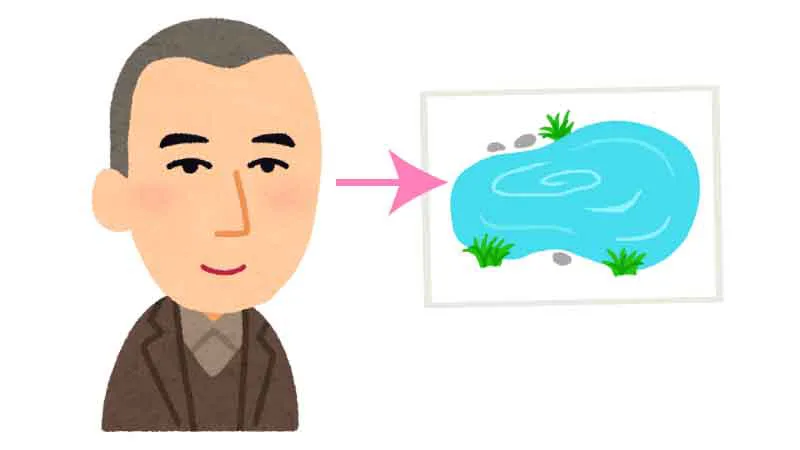
その途端に、賢治の中で、
ここに蟹の親子が住んでいたら、どんな風に暮らしているんだろう…
と澄んだ水の中の世界が心象風景として浮かび、それが幻燈化されていきます。
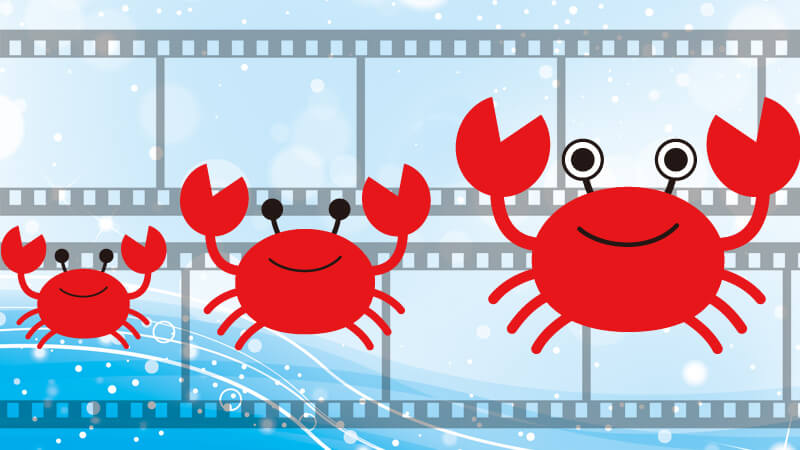
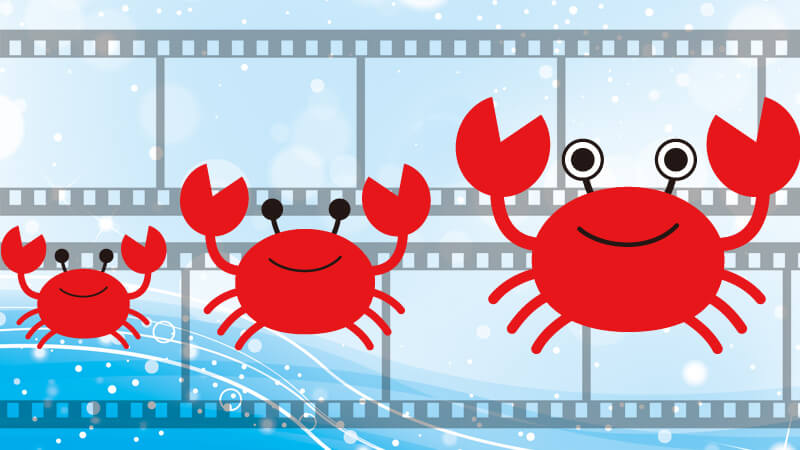
夏と冬だったらどんな暮らしをしているんだろう。
どんな遊びをしているんだろう。
きっと楽しいことだけじゃないはずだ…。
好きなものは何だろう。
そしてそのようなことを想像しているあいだに、賢治は蟹の世界に深く深く入りこんでいきます。
その結果、
幼い蟹の兄弟たちは、天上にある太陽のことはしらない
ということに気づきます。そこで
人の知っている太陽とは違う、カニの知っている水面の太陽を表す言葉が必要だ
と思い、
クラムボン!
という言葉が誕生したと考えます。
「クラムボン」は、宮沢賢治が想像したカニの世界があまりに深くなりすぎたために、日本語では表せない言葉に気づいてしまうことで生まれた、“翻訳不能な言葉”なのかもしれません。



自然への興味と知識が深い、賢治ならではの感性かも✨
「イサド」と共通する言葉の不思議
やまなしには、もう1つ「蟹語」が出てきます。
『もうねろねろ。遅いぞ、あしたイサドへ連れて行かんぞ。』
この「イサド」は、実際にある地名ではありません。けれど文脈からすると蟹の兄弟が行って楽しいと思えるところ=「蟹世界での地名」です。
蟹の世界には地上は含まれません。
なのでこれも、「人間の世界で言うとどの場所」と「翻訳するのが難しい言葉」です。
水の中に住んでいる蟹を想像してみます。蟹の考えるような「地名」は人間の感覚と同じ感覚でしょうか。
例えば深さに関しては、自由に動ける分、人間よりも細かく区分けされてそうな気がします。ひょっとすると水流の強さ、湧き水と流れる水の混ざり具合なども関係したりするかもしれない。
さらに、砂と泥の違いで呼び方を変えたりしているのかも。



蟹の感覚で区分けされたそんな場所も、人の言葉で説明できないですよね
ここも人の世界の言葉でうまく説明ができないので、「イサド」とそのまま蟹語を使っているのだと思います。
やまなしに出てくる2個の造語「クラムボン」と「イサド」は、それぞれ「翻訳できないからそのまま蟹語が残っている」と考えることができます。
私の考えるクラムボンの正体とその理由 まとめ
クラムボンは、蟹語で「水面に映った太陽」のこと。
カニの兄弟は地上~天上のことを知らないので、水面に映る太陽の環を本体として考えて、そのものに「クラムボン」と名前を付けている。
これを作品内で「水に映った太陽」と翻訳しカニに言わせてしまうと、カニの兄弟が天上のことを知っている事になってしまう。なのでここは、翻訳できない。
これがこの部分で「クラムボン」とそのままカニの用語を使っている大きな理由。
宮沢賢治はカニの世界を想像する中で、日本語に翻訳することが困難な言葉があると考え『クラムボン』という造語を生み出した。その言葉は、作品中では翻訳されずにそのままの形で残ることになった。



私はこう考えました。ただし…
賢治自身は「クラムボンはなに?」の解答を明かしていません。
それはきっと、賢治は「答えを教えることよりも、読んだ人が別の世界に考えを寄せること自体に意味がある」と考えていたからだと思います。
だからこそ、その賢治の気持ち通りに、たった五文字の謎は今も読む人の想像を揺さぶり続けます✨
クラムボン=水に映った太陽とする、先行説
最後に、クラムボン=水に映った太陽とする、先行論文をご紹介します。
こちらの論文では、「クラムボン」という言葉の由来についても考察しています。
「宮澤賢治論 : 『雪渡り』から『やまなし』へ」日置 俊次(青山語文 45)
「クラムボン」は「眩む」(まぶしい)と「ぼんぼ」(ぼんやりまるい)という言葉から生み出された造語である。鈍い円形をした眩しいもの、それは川底から水面に見えている太陽である。
宮澤賢治論 : 「雪渡り」から「やまなし」へ(「青山語文」 45 2015-03)
→青山学院大学図書館 蔵書検索システムへのリンク(こちらにあるPDFから読むことができます)
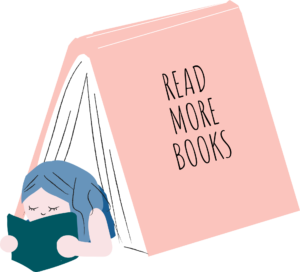
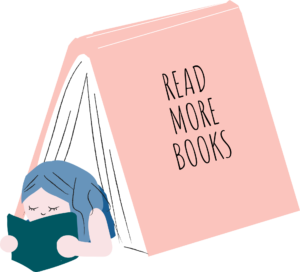
捕捉(飛ばしてもよいです)
実は私の説、一か所あやういところがあるんです…。
この作品には「日光・月光・月あかり」は出てきますが、「太陽・月」本体の表現がない。
これは蟹が天体を知らないことの裏付け…としたかったんですが、実は本文に一か所「月」があったりします。
十二月の「蟹の子供らは、あんまり月が明るく水がきれいなので睡らないで外に出て」という部分です。
カニの会話文ではないので決定的な部分ではないですが、これを読むと、「あれ?蟹の兄弟、月の本体を知ってる?」ってことになってしまい、私の説がちょっとあやうい。
ただ、新聞に載ったやまなしはこの表現でしたが、『やまなし』には初期形があります。
初期形ではこの部分は、
「蟹の子供らはあんまり水がきれいなので睡らないで外に出て」と、「月が明るく」がありません。
この文章なら私の説は通ります。
『やまなし』の章分けは「五月」と「十二月」ですが、初期形では「五月」と「十一月」で、これは新聞に載った時に誤植されたという説もあります。
私としては誤植というよりも、当時の賢治は無名の作家ですし、新聞に載せる際に表現に具体性がでるように校閲が入った?とも思っています。
真相はどうなんだろう。新聞社の生原稿が見たいかな…。



ここまで読んでいただきありがとうございました
こちらの記事では宮沢賢治の『やまなし』の伝えたかったことを、作品全体の構造から考察しています。
【宮沢賢治『やまなし』徹底考察】かぷかぷの正体、賢治が伝えた「別の世界を感じる大切さ」